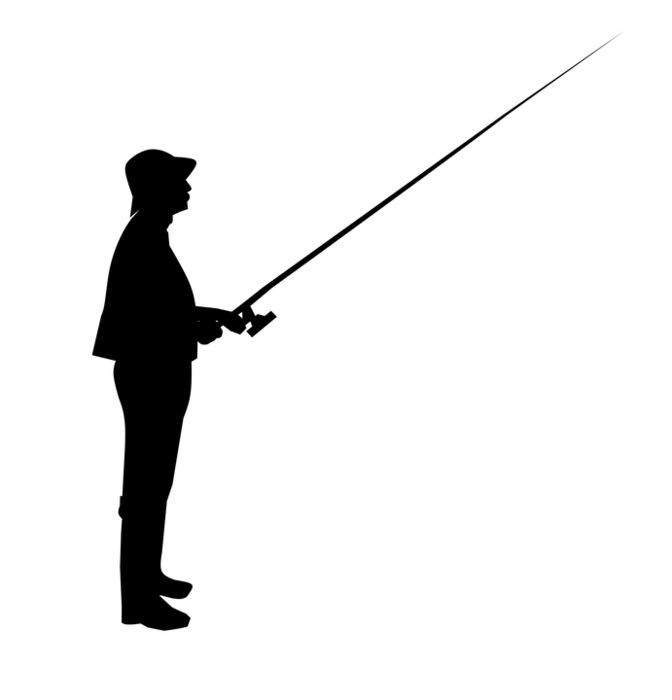日本でヒッチハイクをする割合と男女別ヒッチハイクのコツ
更新日:2025年03月05日

ヒッチハイクとは

日本でヒッチハイクをする割合

男女別ヒッチハイクのコツ

男の子どうしの2人組か女の子どうしの2人組が良いでしょう。なぜ2人組なのかというと1人だと危険な目に可能性があります。特に女性が一人でヒッチハイクをする事は、お勧めしません。(できないわけではないですが、危険度が増します。)
そして3人になるとなかなか乗せてもらえる確率が低くなります。なぜならば、車はヒッチハイカーを乗せようとして運転しているわけではないです。一人一人に目的があります。なので一番いいのが同性同士で2人組のペアですることでしょう。
男子編ヒッチハイクのコツ
そして、声をかける時は笑顔でそして簡単な自己紹介となぜヒッチハイクをしているか。さらに目的地を手短に伝えましょう。そして、車のナンバーを見て行き先を伝えるのも効果的です。
多くのドライバーがインターチェンジなどでする事は、トイレ休憩と簡単な食事ですなので、休憩に行った後の車に戻る際に話をかけるのが良いです。
方向が間違っていないか気を付けて
女子編ヒッチハイクのコツ

2つめは同性のペアでする事です。1人だと怪しまれたりすることもあります。
3つめ車が止まりやすい所に立ってヒッチハイクをし、インターチェンジの前や、信号の手前、近くに駐車場がある所です。
4つめインターチェンジなどでヒッチハイクをする場合は、男性の2人組のペアを捕まえるのが一番効率的です。
5つめは、なぜヒッチハイクをしているか伝えると乗せてもらえる確率はあがります。
笑顔でヒッチハイクしよう
ヒッチハイクは違法なのか

ヒッチハイクそのものより、こういった観点で取り締まりにあう可能性は充分にあります。ですが、ヒッチハイカーを乗せてお金を取る事は違法とされています。なぜならば、自動車に人を乗せてお金を取る際には2種免許が必要です。(タクシーやバスなどのように)
トラックのナンバー
ですが、トラックのを管理する会社は年々厳しくなっています。「運送会社」の社内規定(内部規則)でヒッチハイク(ヒッチハイカーを車に乗せるのが)「禁止」はあります。
これは、万一の事故などの時に「保険」の関係で、ヒッチハイカーへの保証が無理なのと、ヒッチハイカーが原因で、運行に支障が出て「損害」が発生した場合本人特定が難しい上に、損害賠償を請求しても支払能力に問題=運転手負担(最悪:運送会社負担)になるためです。
ヒッチハイクが禁止されている場所もある
これは、ヒッチハイクによる事件が多発したために被害者を増やさないように禁止されています。そして、海外でヒッチハイクをする際は危険が伴いますので十分気を付けてヒッチハイクをして下さい。
ヒッチハイクのときにカバン

ニクソンのリュックサック LANDLOCK III
しっかりしてて普段使いしています。 耐久性も問題なさそう。たくさんはいります。 商品が届くのがとても早い。 通学用に購入しましたが、充分な大きさ、機能、ポケットも多いです。 特に不備もなく、1万越えのバックに少し足を延ばしてみてはいかがでしょうか。
https://www.amazon.co.jp
THE NORTH FACE VAULT(ヴォルト)
何より、ノースフェイスはアウトドア用に作られているので、走ったり山を登るさいに体にフィットするので疲れにくいです。
今まで細かいポケットのないリュックを使っていましたが小物がリュックの中でどこにあるかわからなくなるので不便でした。こちらは前面のファスナーを開けたところに細かい仕切りがあるので小物が迷子にならず便利です。他のコメントにもありましたが自立しないので使いづらいと思う方もいるかもしれません。でもカッコ良さといい仕切りといい満足です。 荷物がとても入って使いやすい。 ポケットも沢山あってとても便利
https://www.amazon.co.jp/
MR.YLLS
ヒッチハイク中にPCや携帯電話を持ち歩くと思うのですが、リュックに防水機能が付いているのは安心です。
外国へ旅行することのため、このリュックを購入しました。 リュックが軽くて丈夫な感じです。グレーと黒混ぜている色が好きになりました。ポケットが多いですから、メガネケースや携帯、パスポートなどそれぞれのポケットに分けて入れられます。とても便利です。 リュックの片側にUSBポートが付いています。よく確認すると、モバイルバッテリーをリュックに入れまして、このUSBポートの向こう側に接続します。こうしたら、スマホを手持ちでも充電可能になります。とても便利な機能だと思います。 飛行機に持ち込むことができました。常用品と着替えの服をいっぱい入れって、想像以上の収納力で満足しました。 今まで二週間ほどしか使用していないですが、よくないところがまだ見つけませんでした。耐用性もまだわからないですが、生地や縫製が良い感じですから、きっと耐用性も悪くないと思います
https://www.amazon.co.jp%E3%80%80
財布
<地球の歩き方オリジナル トラベルスマートウォレット ブラック>
ベトナム旅行用に購入しましたが、コンパクトで使いやすいので、今は常用しています。 この財布に入れているのは、クレジットカード1枚、運転免許証、保険証、1万円札・5千円札・千円札を各1枚、そして、500円玉1個、50円玉1個、10円玉1個、5円玉1個、1円玉1個です。 ふだん現金を使用することはまずないので、こんな財布で充分なことに気づきました。
https://www.amazon.co.jp/
<モンベルmont-bell ジップウォレット>
値段のわりにはしっかりした商品ですが、山歩きやトレッキングでジャンパーやパンツのポケットに入れるには少し大きい感じ。固めの素材でこれ以上折れないので嵩張るかな
https://www.amazon.co.jp
<SmartTravel パスポートケース 首下げ スキミング防止 パスポート ポーチ >
ヒッチハイクの途中で鞄が盗まれぬ何て事も無きにしも非ずです。ですので、主要の財布とは別に少額のお金と必要な物は首から下げ服の中に入れておくことが無難です。いくら、日本が安全とはいえいつ何が起こるか分かりません。
この首下げのお財布は、小銭などは取り出しにくいですが、紙幣や携帯自分の大切な物を一つに集められるのが良いポイントです。
最初は ちょっと大きいかと思いましたが 首からかけてみると なかなか自分の体形には合っているかなと思います ポケットも 結構ついてるし 買って良かったです。
https://www.amazon.co.jp
ヒッチハイクにアプリ

ヒッチハイクをする際はMAPをダウンロードしておきましょう。そして、GOOGLE MAPであれば、オフラインでも使用可能です。もしヒッチハイクの途中で電波が無い届かないとなった時にGOOGLE MAPがあれば無敵です。
何処でヒッチハイクするのが良い
乗せてもらってから目的地を言えば、目的地までは連れていけないけれど○○までなら連れていけるよなんて事も多くあります。ですので、初めから目的地を書くのではなく一番近い街を書きましょう。
そして1時間たっても捕まらない場合は、目的地に問題があるか、立っている場所に問題があります。
ヒッチハイクをするのが良い場所については、下記を参考にしてください。
高速のサービスエリアやパーキングエリア
加速地帯ではしない事。十分泊まれる距離がある所に立つことです。裏技ですが、車のナンバーを見てドライバーの方がどこに行くのかを予想する事ができます。ナンバーや人の雰囲気を見て頼むのも良いでしょう。
サービスエリアやパーキングエリアでトラックに声をかける人も居ますが、白色のナンバーにしか乗れないので気を付けましょう。
国道沿いのIC前
国道の信号付近
高速の入り口周辺
ヒッチハイクが禁止のエリア
ですので、ヒッチハイクをする場合は何処でヒッチハイクをするか。そして、その場所は違法ではないか調べてからしましょう。
ヒッチハイクの時の持ち物
マジックペン

スケッチブック

地図

カメラ

ヒッチハイクは乗せてもらう側にはメリットがあるのですが、ドライバーの方にはメリットはありません。ですので、せめてヒッチハイカーを乗せたなっていう思いでだけでもドライバーの方に返せたら良いでしょう。
ヒッチハイクのメリット

交通費がかからない
コミュニケーション能力がつく
多くの人に会える
そしてこの人達と話した思い出は一生の思い出になること間違いなしです。1つ1つの出会いにドラマがあります。ヒッチハイクをしなければ、得られない体験でしょう。
全国に友人が出来る
ドライバーの方へのマナー
断る勇気も必要
ヒッチハイクをして、乗せてくれると言って居るけれどこの人怪しいと思ったらすぐ断って下さい。「もうちょっと遠くまで乗せて貰いたいので他の人に頼みます」や「さっき声かけた人がい言っていってたので」なんでもいいので適当な理由をつけて断りましょう。
ヒッチハイクをして思い出を作ろう

そして、ヒッチハイクは車に乗り込むまでがヒッチハイクではなく、車から安全に下りるまでがヒッチハイクです。安全第一です。おうちに帰るまでがヒッチハイクなので、最後まで気を抜かないようにしましょう。
では、楽しいヒッチハイクをしてください。一人でも多くの方の参考になれば幸いです。少しでもやってみたいと考えて居る方はぜひチャレンジしてみて下さい、
初回公開日:2018年01月30日
記載されている内容は2025年03月05日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。